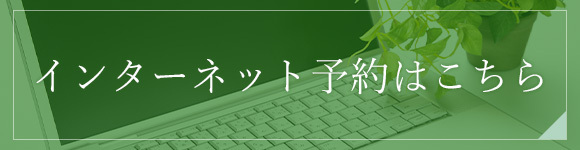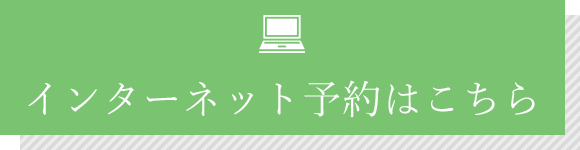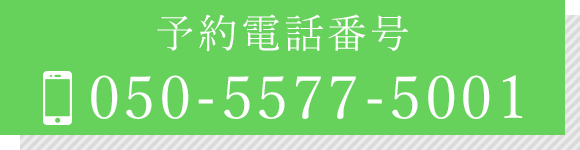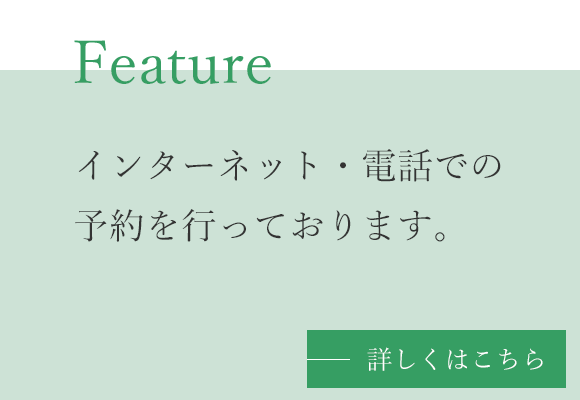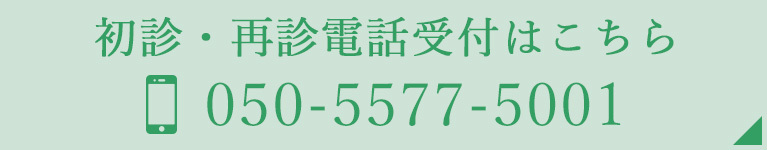足柄上郡開成町吉田島
開成駅
耳鼻咽喉科
私たちが目指すのは、「地域の皆さまに信頼されるかかりつけ医」です。そのために患者さん1人ひとりの健康上の悩みや不安に真摯に向き合い、適切な診療を心がけております。どうぞお気軽にご相談、ご来院ください。
お知らせ
診療時間変更 10/18(水曜) 「午前のみ」の診療になります。 (午後休診です)
■2023/10/05 ホームページをリニューアルいたしました。今後ともよろしくお願いいたします。
■土曜 休診
諸般事情のため 当面しばらく 土曜の診療を休診しております。
■来院前には、体温測定をして下さい。
診察中も原則マスク着用願います。
他の受診者への迷惑・不安にもなりますので、マスクをしない方の来院は、ご遠慮願います。
※急な「嗅覚障害・味覚障害」症状の方は、まずは1週間、他人との接触や受診を控えてください。
その後も、発熱・呼吸器症状等なく、「嗅覚症状が持続」している場合には、耳鼻科診療へとなります。
新型コロナ 感染後の諸症状への対応
院内空間の「除菌」励行中!
「除菌水」のミスト、プラズマクラスターファン、HEPAフィルター空気清浄器など
室内空間の衛生対策・清浄化に努めております!&待合室・診察室 常時換気中です!!
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ |
| 午後 | ● | ● | ● | - | ● | - |
■診療時間
午前 9:00~
午後 15:00~
▲土曜 予約者のみ(不定期で休診あり)
※補聴器相談:隔週(第2、第4週のみ)
水曜 14:30~16:00
詳細はこちら ≫
■受付時間
午前 8:45~11:00(以降は予約者のみ)
午後 14:30~17:00(以降は予約者のみ)
■休診日
木曜・土曜午後・日曜・祝日
「予約順」の診療です。*1枠(15分毎)に、数人ずつの予約が入る仕組みです。「同枠」内では、窓口での先着順となります。☆予約時間の5-10分程度前に来院してください。
*予約枠には限りがあります。時間を過ぎてしまった診療受付は、原則お断りさせていただいております。
診療予約
「初診」や、「月代わりで再診」の方は、必ず保険証をご提示ください。(コピーは不可)
※保険証は、「受診日現在で有効」な保険証を提示願います。
「新しい保険証が来ないから」といって、「すでに失効している保険証」を受診の際に提示する方が散見されます。
これは通用しませんのでご注意願います。
<新たな保険(国保or健保)適用になった日から、それ以前の保険証(健保or国保)は無効になります。
たとえ、旧証の「有効期限」以内であっても、その旧証は無効です。>
あらたな保険証の発行が遅れている場合でも、相応の「証明書」を入手してから、受診してください。
*初診・再診問わず、「各月で初回」の受診時には、保険証確認が必要とされています!!
保険証の「提示」とその「確認」は、保険診療を行う上で「受診者」と「医療機関」それぞれの義務となっております。
当院の特徴
医療法人社団 遠藤耳鼻咽喉科医院のご案内
■院長名
遠藤 圭介
■所在地
〒258-0021
神奈川県足柄上郡開成町吉田島4364-4
■診療科目
耳鼻咽喉科
■電話番号
0465-82-3536